“俺たち”という主語を失った物語として見る『おそ松さん』2期
『おそ松さん』2期が終わってしまった寂しさが一ヶ月経っても癒えないので溢れる想いを書き殴ろうと思う。
松については1期のとき論文かよという文量で感想を綴りましたが、その後も飽きることなくDVDを観返して松とは何だったのか考えつづけてきました。それで思ったのが、『おそ松さん』は“俺たち”という主語を失い、“俺”として生きることになった寂しさと痛みを描いた物語とも言えるな、ということ。1期エンディングで「俺があいつで俺たちが俺!」と高らかに宣言していたカラ松が、24話で「俺たちは……いや俺は」と言い直したことに象徴されるように。
この“俺たち”という主語は、昭和から平成にかけて、現実社会を生きる私たちが失ったものでもあります。核家族化が進み、血縁も地縁も薄れ、地域共同体の代わりに機能していた会社という共同体も終身雇用制度の崩壊と共に失われ、共同体の一員としてではなく個として生きていかなければならなくなった。そこにはロールモデルもわかりやすい規範(「結婚して・働いて・子どもを作れば大人の仲間入り」みたいなもの)がないから、若者はどうしたらいいのかわからなくて戸惑ってしまう。
とこう書くといかにも現代社会特有の問題のように響くけど、1期23話「ダヨーン族」を見返して、「あぁ、これは原初的な痛みなんだ」と感じました。
おそ松はダヨーンの体内で、誰もがダヨーンと化した世界についてこう語ります。
「顔も言葉も立場も同じ。そこから生まれる底なしの穏やかさと安心感。それこそがダヨーン族の真髄ダヨン」。
ダヨーンの体内がジョゼフ・キャンペルの神話論でいう「鯨の胎内」で、6つ子が母親の胎内にいた頃の状態であることは以前も述べました。
そしてこれは、何も6つ子に限ったことではないのです。誰しも胎児の頃は母親とつながっているし、誕生後も乳児は1歳位まで自他の区別はついていません。言葉の習得と共に、自分と母親は別個体であること、ものには名前があることを学んでいきます。
水が蒸発して雲となり雨として降り注ぎ川や海になるように、あらゆるものは形を変えながら循環しています。世界は連続していて、本来は明確に区切ることなどできない。でもそれだと不便だから、人はあるときの状態を暫定的に「雲」と「川」を区別するのでしょう。
分けて名前をつけることで対象を認識し、理解することができる。愛することもできる。
一方で、分けて名前をつけることは連続した世界に楔を打ち込むことでもある。世界から切り離される痛み、本質を見失う不安。きっと誰もが共通して経験してきて、いつか忘れてしまった戸惑い。
でも、発達段階において6つ子はその経験が曖昧だったんじゃないかなと思います。乳幼児は鏡に移る自己と他人の像を見ながら自己を認識し自我を形成していく、とかなんとかラカンが言っていたと思いますが、いや自分と同じ顔6つもあるけど!? 右を見ても同じ顔、左を見ても同じ顔!! しかも大人は俺の顔を見て「おそ松」と話しかけるけど、たまにあいつも「おそ松」って呼ばれてるし、みんなひっくるめて「おそ松たち」と言われることもあるんだけどどういうこと!?
と彼らが戸惑ったかどうかは知らないけど、こんな環境じゃそりゃ俺があいつで俺たちは俺!ってなるのも仕方ないことですよね。自他の境界線が引けなくて当然。
けど、23話で彼らはそんな世界と訣別して、24話では社会に飛び出していくわけです。しかし25話で全てがひっくり返され、2年のブランクを経てふたたび童貞ニートの物語として2期が始まりました。
……というのが私が二期を語る上での前提です。前提長いって? 当たり前でしょ!! 松についてのブログ書くの1年ぶりなんだから!!!!!! この溢れ出る!!!!!! 想い!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ということで次回からようやく本題です。
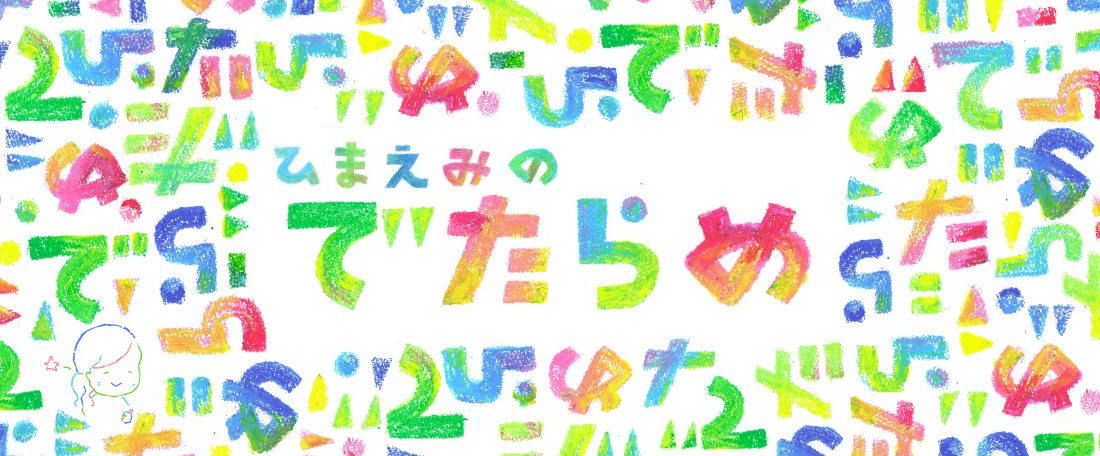
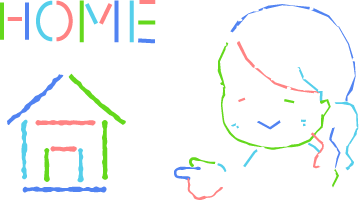







コメントを残す